東北大学加齢医学研究所教授の川島隆太氏が【朝食と脳の働き】において、衝撃的な発表を行いました。
それが、朝食のおかずを増やすことによって、子供の学力に差が出るということ。
これはどういうことなのでしょうか。
川島教授いわく、まず小学生の頃から平日のほぼ毎日、朝食を食べていた大学生は、朝食をほとんど食べなかった大学生と比べ、偏差値65以上の大学に第1志望で現役合格している割合が高いとのこと。
また認知機能を点数化できるテストがあるのですが、同じ人でも朝食を食べた時、また食べない時を比べてみると、午前中の脳の働きに10%~20%の得点差が表れています。
そして何よりも重要なのが朝食の内容。
これも違いがあるそうです。
まず主食。
お米のごはんを食べている子供は、パンを食べる子供に比べて知能指数が高い傾向にあり、脳の神経細胞層の量も多い事がわかっています。
お米って重要なんですね。
さらに川島教授はおかずの重要性についても指摘しています。
でもここでもうひとつ指摘があり、単に朝食を食べれば良いという事ではなく、おかずの品目が多いほど、子供の脳はよく働き、よく成長するそうです。
普通、朝食といえばおにぎり1個、パン(ト―スト)1枚といったカンジですよね。
しかし川島教授の研究結果によると、
・炭水化物だけの朝食
・主食、主菜、副菜が揃った朝食
これらをそれぞれ食べた時を比べてみると、同じ人でも午前中の認知機能テストで得点差が生じ、おにぎりもしくはパンだけといった炭水化物のみのときには低い成績が出ていたのです。
また脳機能イメージング研究という脳の活動を調べる研究があるのですが、大学生の協力のもと、
・朝食として栄養バランスのとれた流動食
・同量同カロリーの砂糖水
この2種類の朝食をそれぞれ摂取した時の認知機能テストの結果を比べてると、流動食をとったときのほうが、脳が活発に働いていたという結果が出ています。
こうやって見てみると、明日から朝食を変えればいい!と思う人もいるでしょう。
しかし川島教授が強調しているのは朝食の向こうにある親の意識の問題です。
日本の小学校は、ほぼ給食があり、また夕食は食べ過ぎが指摘されているくらい豊富。
でも唯一バラツキがあるのが朝食なんですね。
バランスのとれた朝食を食べるかそうでないか。
これは家庭による経済状況の違いとかは、あまりには関係がなく、あるのは親の意識の差によるものと指摘しています。
さらにかつて川島教授が文部科学省と共同で全国の小中学生の認知機能を検査した事があります。
その時、生活習慣も調査したのですが、朝食でおかずを食べていない子供が約40%いたそうです。
また同時に保護者の意識調査も行ったのですが、その結果、『朝食の栄養バランスが大事であると知っているか』との問いに対し、
・「知っている」
・「おおむね知っている」
この2つを合わせても、全体の60%しかいませんでした。
つまり、とりあえず朝食を食べればいいと考えている親が約40%ということです。
この数字は、朝食でおかずを食べていないという子供の割合に合致しますね。
私の感想ですが、実は私は小学生の頃、あまり朝食を摂らない子供でした。
理由は、朝寝坊。
家を出るギリギリまで寝てたんです。
だから朝食をほとんど食べる事ができなかったんですね。
でも確かに朝食を食べた方が、考える力というか、頭が冴えます。
それは社会人になった今もそうです。
あと、ダイエットというのもありました。
小学校高学年になると、太りたくないという意識から、休みの日でも朝食を摂らなかったんです。食べると太るという考えです。
でもこれは今となっていろいろと調べてみるとマチガイで、食べ方、食べる量によってコントロ-ルできます。
なので自分の子供には、おかずを多くした朝食を少量でもいいから食べる様に心がけています。
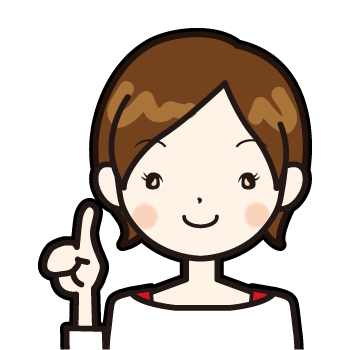
・パンよりもごはんを食べる子供の方が知能指数が高い傾向にある
・主食の炭水化物だけでなく、おかずが重要





